こんにちは、防災母さんです!
2022年8月20日(土)、名古屋大学で開催された防災士養成研修講座、愛知県「防災・減災カレッジ」の「地域防災コース」・「防災VCoコース」1日目に参加しました。
この日は「地域防災コース」と「防災VCoコース」の同時開催で、どちらか1コースの選択となります。
それぞれ2日間のカリキュラムですが、1日目は共通のため、同じ会場で講義を受けました。2日目は別の日に、分かれて受講します。
「地域防災コース」は、「防災活動に積極的に取り組んでいる自主防災組織の事例やワークショップ等を通じて、地域防災力の向上策などについて学ぶ」市民講座です。
「防災VCoコース」は、「災害ボランティアセンターの設置・運営体験等を通じて、ボランティアコーディネーターの知識・技術を学ぶ」市民講座です。
この2コースは、「防災士」の資格を取得するための選択講座の一つとなっています。
今回は講義が5時間ありました。そこで、1時間目から3時間目を「まとめ(前編)」、4時間目から5時間目を「まとめ(後編)」として、2回に分けて、この講座で学んだことの概要と、私の感想についてご紹介します。
カリキュラム
この講座のカリキュラムは以下のとおりです。
| ①9:30~10:30 | 地域防災力の向上 | 認定特定非営利活動法人 レスキューストックヤード 常任理事 浦野 愛 | |
| ②10:40~11:10 | 災害時の要配慮者支援 | 愛知県福祉局 地域福祉課 職員 | |
| ③11:20~12:20 | 避難所運営 | 名古屋大学 減災連携研究センター 特任准教授 木作 尚子 | |
| ④13:20~14:40 | 先進事例紹介 (自主防災組織等) | ①大府市共和西自主防災会 会長 三澤 誠 ②豊橋市岩田校区自主防災会 会長 山口 智雄 ③防災ママかきつばた 代表 高木 香津恵 | |
| ⑤14:50~17:00 | ワークショップ 「地域防災力を 高めるための アイデア出し」 | ①認定特定非営利活動法人 レスキューストックヤード 事務局長 浜田 ゆう ②名古屋みどり災害ボランティア ネットワーク 代表 岡田 雅美 |
講義の前にあったこと
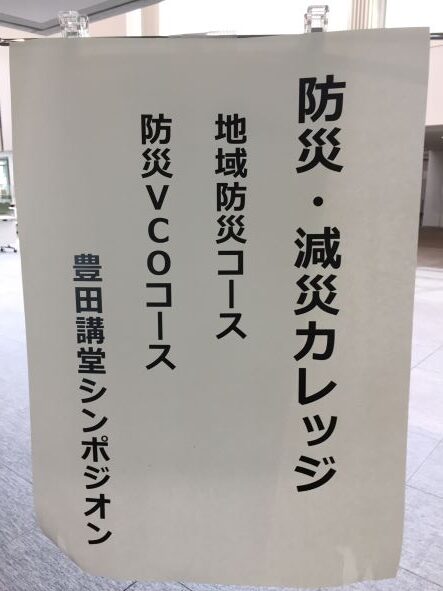
会場の名古屋大学の豊田講堂シンポジオンに着くと、アルコール消毒、検温の後、受付を済ませて、書類と名札を受け取りました。
豊田講堂シンポジオン内の席は自由席でした。豊田講堂ほどは広くなかったのですが、全てのドアが全開で、換気に気を付けていることがわかりました。
名古屋大学が夏休みで、大学内の学食等がすべてお休みのため、ロビー内で昼食を取るか、学外で食事を取ってください、と言われていました。
また、資格認証カードの発行が必要か、不要かを記入して、用紙を提出して下さい、と言われていました。資格認証カードは、愛知県「防災・減災カレッジ」の修了するコースによって種類が変わってきます。発行を希望すれば、防災・減災カレッジの①「防災リーダー証」、②「防災ボランティアコーディネーター証」、③「まちづくりアドバイザー証」のいずれかを受け取ることが出来ます。
それと、「防災士」資格取得を希望している方は、前回までに発行してもらっている、「市民防災コース」の修了証を来週以降の2日目のコースの時に、必ず持ってきてください、と言われていました。来週以降の2日目コースを修了すると、いよいよ「防災士」資格の受験の申し込みが出来ます。
今回学んだことと感想
①「地域防災力の向上」では、認定特定非営利活動法人 レスキューストックヤード 常任理事 浦野先生より、以下のような内容について講義がありました。
・南海トラフ地震が発生した場合の被害想定者数と想定震度について。
・阪神淡路大震災による主な死因とそこからの教訓について。
・台風や集中豪雨による家の被害と対応策について。
・避難所生活の注意点について。
・地域防災活動の具体例について。
・地域防災活動を継続するために必要なことについて。
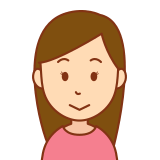
南海トラフ地震で、死者数23万1千人予想(最大値)にかなりショックを受けました。地域の防災力を高めることは、災害時にその地域の復旧が早くなるということにつながりますね。
②「災害時の要配慮者支援」では、愛知県福祉局 地域福祉課 井上先生の講義より、以下のような内容について講義がありました。
・「要配慮者」と「避難行動要支援者」について。
・「避難行動要支援者名簿」について。
・「個別避難計画」について。
・災害が起きた場合の要配慮者の避難支援について。
・「一般難所」と「福祉避難所」の違いについて。
・避難所の福祉支援について。
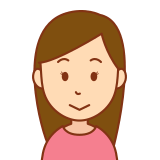
要配慮者の方が優先的に避難できるような福祉避難所があると、災害時にも安心だと思います。
③「避難所運営」では、名古屋大学 減災連携研究センター 特任准教授 木作先生より、以下のような内容について講義がありました。
・災害による人間への影響について。
・過去と現在の避難所の状況の変化について。
・避難所の多様化について。
・感染症流行時の避難生活の注意点について。
・「福祉避難所」と「指定福祉避難所」について。
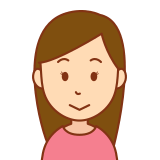
災害が起きた時、もし避難所で生活するとなったら、自分の生活の場だと考えて、他力ばかりを望むのではなく、自分たちでやるという意識が必要ですね。
前編まとめ
今回は、地域防災の講義を主に聞くことが出来ました。最近、全国のどこかで台風や集中豪雨などによる水害が毎年、起こっているのではないかと思います。水害で避難するといったことも他人事ではなく、いつ自分の身の回りに起きても、おかしくない状況です。
最近では、避難所は多様化してきており、在宅避難や車中泊といった選択をされる方も多いようです。ただ、要配慮者が優先的に入れるような避難所があると、そういった方がいるお宅では、やはり安心ですね。
地震災害での避難場所や水害での避難場所を、自分の中だけでなく、家族の中で話し合っておきたいと思います。
次回は「地域防災コース」・「防災VCoコース」1日目の後編に続きますので、お楽しみに!
♢♢♢
防災士試験に向けて試験勉強をされている方は、以下の記事も参考にしてください。
これから防災士試験に挑戦しようかなと考えている方は、以下の記事も参考にしてください。
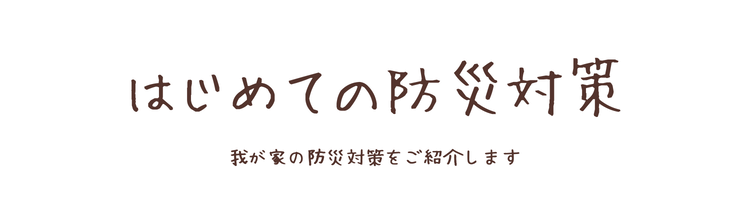


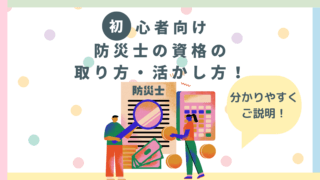


コメント