こんにちは、防災父さんです!
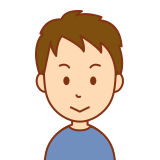
今回は、日曜大工的な内容なので、僕の出番ですね!
早速ですが、お家の中の地震対策で、最初にやるべきことは何でしょうか?
答えは、タンスや本棚などの転倒防止対策です。
何故なら、いくら非常食や防災用品を用意していても、家具の下敷きになって死んでしまったら使えないからです。
そのため、自治体では、何はともあれ、家具の転倒防止を啓蒙されているのですね。
私の住む愛知県でも、以下のようなパンフレットでPRされています。
このパンフレットにも紹介されているように、一般に、家具の転倒防止器具としては、
- L字金具
- 突っ張り棒(ポール式器具)
- 粘着ベルト
- ワイヤー
- ストッパー(家具の下に挟む物)
などがありますね。
ただ、分かっていても、「実際、何をどうしたら良いのか分からない」という方も多いのではないでしょうか?
そこで、ここでは、我が家のケースを一例として、家具の転倒防止器具の取り付け方をご紹介します。
これを読めば、具体的なイメージがつかめ、まだの方もやる気が湧いてくると思いますよ。
また、既に対策されている方も、点検や見直しの良い機会になること間違いなしです。
最後までざっと見て頂き、必要なところだけ参考にして頂ければ幸いです。
家具の転倒防止器具の取り付け手順
家具の転倒防止器具の取り付け手順は、以下のようになります。
- (手順1) 住まいの種類や構造を確認する。
- (手順2) タンスを固定する壁の下地材がどうなっているか確認する。
- (手順3) 固定する家具のどこを固定するか決める。
- (手順4) どのような器具で家具を固定するか決める。
- (手順5) 材料と道具を用意する。
- (手順6) 固定器具を壁と家具に取り付ける。
このうち、(手順1)~(手順4)のところで、住まいの種類や壁の下地材、固定する家具によって、やり方が変わってきます。
具体的には、
- 賃貸住宅か持ち家か(ネジが打てるか、自分だけの判断で良いか)
- 木造住宅か鉄筋コンクリートのマンションか(壁が木か、コンクリートか)
- 木造住宅でも2×4(ツーバイフォー)か木造軸組工法(在来工法)か
- 木造軸組み工法でも下地材が縦横どのような間隔で配置されているか
などによって異なってきます。
下記資料に詳しく記載されていますので、これを参考にしつつ、自宅の壁の状況をよく確認し、適切な方法を選択します。
以下、(手順1)~(手順6)について、我が家を例として具体的に説明します。
(手順1) 住まいの種類や構造を確認する
最初は、住まいの種類や構造を確認します。
我が家は、自己所有の木造一戸建てです。
ですので、自己判断で壁や柱にネジを打つことができます。
家の作り方は、木造軸組工法です。
ですので、壁の構造は、下地材(柱や間柱など)の上に石膏ボードが貼ってあり、その上に壁紙が貼ってあります。
これは、建築図面でも確認できます。
(手順2) タンスを固定する壁の下地材がどうなっているか確認する
下地センサーで下地材の位置を大体把握し、家具との位置関係を確認します。
下地センサーの使い方については後程詳しくご説明しますが、この段階で入手して確認した方が良いと思います。
転倒防止器具を固定する際、家具との位置関係をみながら、
- 縦方向の柱や間柱(まばしら)にするか
- 横方向の横木や桟(さん)にするか
- 追加の木材が必要になるか
など、固定箇所の見当を付けておきます。
(手順3) 固定する家具のどこを固定するか決める
今回固定する家具は、洋服ダンス二つ、ハイチェスト(背の高い引き出しのみのタンス)一つです。
洋服ダンスは高さ2mくらい、ハイチェストは高さ1.5mくらいです。
洋服ダンスは壁にピッタリ付けて、2つ並べて配置します。
洋服ダンスの上面を壁に固定するしかありません。
ハイチェストの方は、すぐ上に窓があり、カーテンを開け閉めできるようにしたかったので、壁から少し離して固定することにしました。
ハイチェストの背面が空いているので、背面に固定することにしました。
(手順4) どのような器具で家具を固定するか決める
洋服ダンスは背が高く、壁にピッタリ付けて設置します。
そこで、最も強度が高いとされる「L字金具」で、壁とタンス上面をガッチリ固定することにしました。
また、「突っ張り棒」が余っていたので、念のため付けておくことにしました。
ハイチェストの方は、壁から少し離して「転倒防止ベルト」で壁と家具背面を固定することにしました。
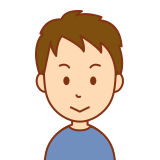
この部屋は寝室なので、夜中に地震が来てタンスが倒れてきたら、ひとたまりもありませんね。そのため、引っ越してきた時、真っ先にタンスの転倒防止をしました。
ここからは、それぞれの家具について、固定方法を説明します。
(手順5) 材料と道具を用意する【洋服ダンス編】
まずは、洋服ダンスの固定方法です。
こちらは「L字金具」をメインにして、「突っ張り棒」を補助として付けました。
最初に材料を用意します。
我が家では、L字金具とネジはホームセンターで買い、突っ張り棒は以前大型スーパーで買いました。
L字金具やネジも色々な材質・形状・サイズの物がありますので、取り付け方をイメージをしつつ、お値段と強度も考えながら決めます。
取り付けが簡単で、なるべく安くて頑丈そうな物にしました。
突っ張り棒は、以前マンションで使っていたものですが、余っていたので、L字金具の補助として取り付けることにしました。
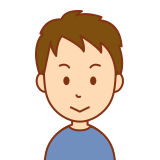
突っ張り棒は単独ではなく、併用すると良いと言われていますね。
続いて道具です。
我が家の場合は、下地探し器具を購入しましたが、それ以外は手持ちの道具を使いました。
材料や道具で手持ちの無いものは買い揃えておきます。
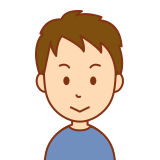
ネットで注文しておくと早いですね。届いたら、あとは付けるだけです。
(手順6) 固定器具を壁と家具に取り付ける【洋服ダンス編】
洋服ダンス上面の掃除
作業に入る前に、洋服タンスの上面を掃除しておきます。
ネジ止めする壁の下地探し
洋服タンスの上面と壁にL字金具をネジ止めするため、下地センサーで壁の中の下地材の位置を確認します。
L字金具でタンスを壁に固定するには、下地材の位置を正しく把握しておくことが一番大事です。
下地センサーの使い方はとても簡単です。
我が家のセンサーは、壁に当てて右手の親指でスイッチを押したまま、左右または上下に動かして下地材を探します。

下地材の無いところからあるところに移ると、その瞬間に「ピーッ」と音がして赤いランプが点灯します。
赤色の光線が指し示すところが、柱や間柱の端です。
下地材の位置を探し当てたら、鉛筆で壁に印を付けておきます。
下地材の太さが分かるように、下地材の両側に印をつけます。
我が家の下地センサー(Zircon StudSensor Pro SL)の使い方について、メーカーのZircon社からYouTubeの動画が公開されていました。文章の説明だけではイメージが掴みにくい場合は、こちらも合わせてご参照ください。
さて、下地センサーで下地材の大体の位置が分かったら、「どこ太」で実際にプッシュピンを壁に刺して、本当に下地があるか確認します。

このように、下地(この場合横木)がないところに刺すと、ピンが全部刺さります。(白いメモリが見えません)
この高さではネジで固定できません。(写真はねじ止めした後に撮影したものです。)

下地があるところに刺すと、ピンが途中までしか入りません(白いメモリが見えます)。
壁に書いた鉛筆の線が下地の横木の幅です。
この高さなら確実にネジで固定できます。
「L字金具」の取り付け

下地材の位置が確認できたら、下地材にL字金具を取り付けて行きます。
我が家の場合、洋服タンスのすぐ上の壁の中に横木が入っていたので、壁側はそこに取り付けました。
また、洋服タンスの上のL字金具を取り付ける位置は端にしました。
我が家の洋服タンスは、端が一番硬くて丈夫で、それ以外の洋服タンスの上面は薄い板だけでした。
L字金具を洋服タンスの上の端に置いたら、L字金具の穴にネジ止めしていきます。
こうして、洋服タンス上面と壁をL字金具でしっかり固定します。
「突っ張り棒」の取り付け

最後に、突っ張り棒を設置します。
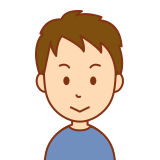
こちらの方が取り付けは簡単ですね。
突っ張り棒は洋服タンス上面から天井までの高さより1センチほど短めにして、中央のツマミをねじって長さを固定します。
突っ張り棒を洋服タンス上面の奥の方(壁際)に立てます。
この時、ツマミの部分を壁の方に向けて立てると、洋服タンスを正面から見た時目立たなくなり、見栄えが良くなります。
突っ張り棒の下端にある歯車状のグリップを「のびる」と書いてある方向に回して、天井に押し付けるように伸ばし圧着させます。
我が家の突っ張り棒は古いためか、脚にネジ穴があるタイプでしたので、念のためネジでも固定しました。
こうすると、地震の時に少しははずれにくくなると思います。

こうして洋服ダンス2つとも、L字金具と突っ張り棒が両端に設置できたら完成です。
(手順5) 材料と道具を用意する【ハイチェスト編】
続いてハイチェストの固定方法です。
こちらは、すぐ上にカーテンがあるので、壁から10センチほど離して転倒防止ベルトを取り付けました。
材料は転倒防止ベルトと木ネジです。
我が家では、家具とセットでついて来たネジ固定式のものを使いました。
最近は色々な壁に対応できる粘着テープ式のベルトも増えているようです。
(手順6) 固定器具を壁と家具に取り付ける【ハイチェスト編】
ハイチェスト上面の掃除
こちらも雑巾で水拭きして掃除しました。
ネジ止めする壁の下地探し
壁の下地の探し方は同じです。
カーテンの開け閉めに邪魔にならないところに、転倒防止ベルトの金具をネジ止めしました。
「転倒防止ベルト」の取り付け

転倒防止ベルトの金具をハイチェストの背面にもネジ止めします。
そのあと、ベルトで接合します。
これをハイチェストの両側に設置したら完成です。

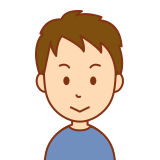
カーテンが入るように、壁から10センチほど離しました。転倒防止ベルトがあっても、カーテンを閉めることができました。
まとめ
今回は、我が家のケースを一例として、家具の転倒防止策についてご紹介しました。
器具としては、L字金具、突っ張り棒、転倒防止ベルトを使いました。
ただ、地震対策というのは「ここまでやれば、絶対大丈夫」とはなかなか言い切れないのも事実です。
しかし、地震はいつくるか分かりませんので、「早めに」「できるところまで」でもやっておくことが大事です。
また、一度設置したら終わりではなく、時々点検や見直しをすることも大事です。
繰り返しになりますが、地震への備えとしては、非常食や防災バッグなどよりも、真っ先に家具の転倒防止をする必要があります。
まだ対策をされていない方は、本記事を参考に、ご自宅の状況にあった方法で、早めに対策をされることをおススメします。
この記事が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。m(_ _)m
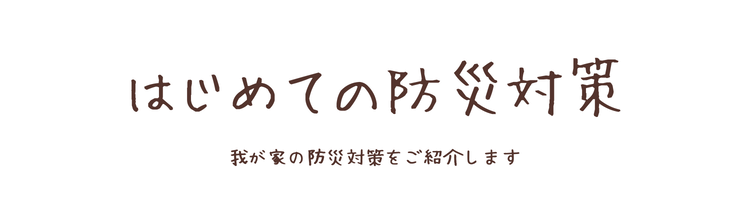




コメント